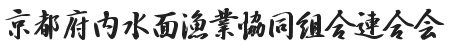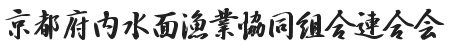- (1)コイヘルペス病のまん延防止について
- コイヘルペスウイルス病(以下「KHV病」という。)は水を介してコイに感染が広がります。
KHV病はコイ特有の病気で、人に感染せず感染したコイを食べても人体に影響はありません。
発症したコイは餌を食べなくなるとともに行動が鈍くなり、エラの退色やびらん等の症状が見られ、死亡率が高い非常に恐ろしい病気です。
この病気のまん延を防止するため、次の御協力をお願いします。
- 釣ったコイを他の池や河川に放流しないでください。
- 河川でコイの大量死を確認された場合は、下記の京都府広域振興局農林商工部、若しくは水産課まで連絡をお願いします。
|
コイヘルペスウイルス病の疑いのある場合の連絡先
| 京都府広域振興局等 |
電話番号 |
所管区域 |
主な河川 |
| 山城 |
農林商工部企画調整室 |
(0774)-21-3229 |
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久世郡、綴喜郡、相楽郡 |
淀川、宇治川、木津川 |
| 南丹 |
農林商工部企画調整室 |
(0771)-22-0371 |
亀岡市、南丹市、船井郡 |
大堰川、保津川、栢原川、美山川、和知川 |
| 中丹 |
農林商工部企画調整室 |
(0773)-62-2743 |
福知山市、舞鶴市、綾部市 |
上林川、由良川 |
| 丹後 |
農林商工部企画調整室 |
(0772)-62-4305 |
宮津市、京丹後市、与謝郡 |
宇川、筒川、離湖 |
| 京都市 |
農林振興室農業振興整備課 |
(075)-222-3352 |
京都市 |
上桂川、保津川、賀茂川、淀川、久多川 |
| 京都府水産課 |
(075)-414-4996 |
向日市、長岡京市、乙訓郡、その他府内全域 |
- (2)アユ冷水病のまん延防止について
- アユ冷水病は、病原菌(フラボバクテリウム・サイクロフィラム)の感染により起こる病気で、今では国内の多くの河川で発生しています。
主に17℃以下の低水温で発生することが多いようですが必ずしも低水温時に限られるものではなく、22℃前後まで発生します。病原菌は冬季に河川に残留することはないと言われております。
症状は下あごや体表から出血したり、体の表面にえぐられたような穴があくこともあります。
アユ冷水病は病気のアユが持ち込まれることによって、他のアユに感染して病気が広がります。従って、アユ冷水病を防ぐには病原菌を持ち込まないこが重要となります。
この病気のまん延を防止するため、次の御協力をお願いします。
- 一度使ったオトリアユや釣ったアユを別の河川でオトリとして使わないでください。
- 釣りから帰ったら釣具やウエダー等を天日乾燥させるかアルコール消毒してください。
|
- (3)カワウによる食害防止について
- カワウは、1970年代には全国で約3,000羽程度まで減少していましたが、その後の保護対策により1980年代には増加に転じ現在では約15万羽程度にまで増加していると言われています。
平成24年の調査では、京都府内で9箇所の塒(ねぐら:集団で寝る場所)と1箇所のコロニー(集団営巣場所)が確認されており、冬季に1,059(12月)羽、夏期に746(7月)羽のカワウを確認しています。
カワウ1羽は1日に約400~500gの魚を補食すると言われており、年間に1羽が150㎏の魚を食害する計算になります。このため、放流したアユやハエ、フナなどが食害されるなど内水面漁業に極めて深刻な影響を与えています。
そこで、各漁協では猟友会等の協力を得て、駆除を行うとともに、放流後の稚アユを守るため、ヒモ張りによる河川へのカワウの着水防止や見回り追い払いなどの対策を実施していますが、カワウは繁殖力・学習能力にも優れており、また広域に移動することから駆除や防除にも限界があるのが現状です。
遊漁者の皆様にもこの現状を御理解いただき、次の御協力をお願いします。
 |
| カワウのコロニー 一巣で2~3羽が巣立った。(2011年5月、京都府南部) |
 |
| 数十羽の集団で魚を捕食するカワウ(2011年12月、保津川) |
|